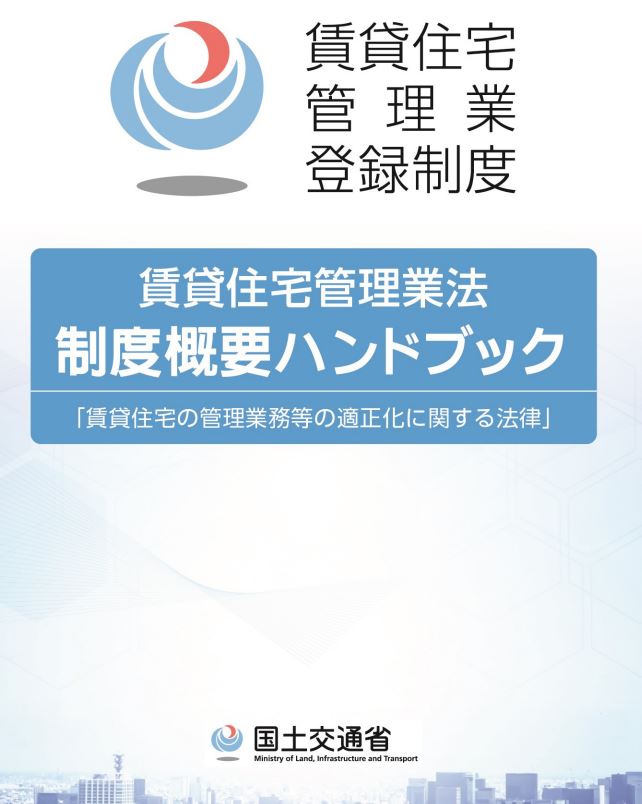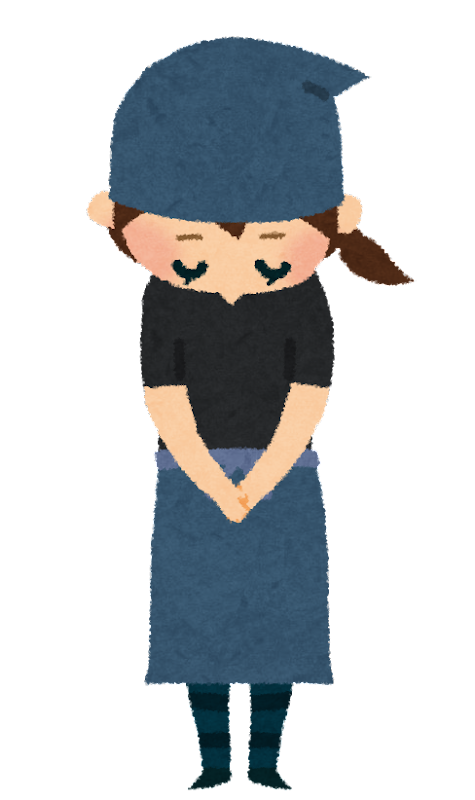【土地活用】土地を事業者に貸す時(コンビニ編)

みなさんこんにちは!
今回は、所有している土地を、事業用途で使用したい事業者様へ賃貸するときのポイントをご説明したいと思います。
その中でも特に、コンビニの用途での賃貸の場合に絞ってご説明させていただきます。
コンビニが土地を借りるときの契約方法
既存の建物に入居する場合と違い、土地からコンビニを始める場合は主に2種類の契約パターンがあります。
土地からのコンビニへの賃貸は2パターンある
一つは事業用定期借地権契約を交わし、借主(法人)自身で建物を建てる場合です。もう一つは土地の貸主に建築協力金というお金を貸し付け、貸主が建物を建てる場合です。
それぞれ詳しくご紹介します。
事業用定期借地権とは

事業用定期借地権とは、事業用(ビジネス)の用途に限定して、土地を貸す時に設定する借地権のことです。契約期間は10年~50年未満の範囲で設定できます。契約終了時は更地の状態に戻して土地が返還されます。
この借地権には次の3つの特約が伴います。①契約の更新はしない②契約終了時の建物買取請求権は発生しない③建物の再建築による契約期間の延長はしないという3つです。ただ、契約期間が30年~50年未満の場合は上記の特約の設定は任意となります。
コンビニ大手が提案する契約書には、だいたいこれら特約は全て約款に記載されていますが、契約する前によく条文を確認しましょう。
事業用定期借地権のメリット・デメリット
この契約の最大のメリットは、貸主側でのリスクが少ない点です。
まず、建物を自分で建てないので、契約時に金融機関などからお金を借りる必要もなく、持ち出しが全くないのは魅力的だと思います。また、建物と違い、貸地なので相続時にもある程度柔軟に対応できます。
ただ、敷地+建物を貸す場合に比べると、家賃は低くなる傾向にあります。
建築協力金とは
建築協力金 (建協金) とは土地の借主側が、貸主に建設費用の一部(もしくは全部)を貸す形で差し入れるお金のことです。
建設費用のうち建築協力金をどこまで差し入れるかは立地やその時のテナントの状況によります。
テナントはこの建協金を払い、土地所有者に建物を建ててもらい、通常の建物賃貸借契約を貸主と結び、家賃を支払います。
貸主は月々の家賃の一部から建協金の返済を行います。
建築協力金のメリット・デメリット
建協金のメリットとしては、テナントが直接お金を貸してくれるので、銀行からの融資は受ける必要がないということがあります。また、先程の事業用定期借地権の契約に比べ、賃料も高額になる傾向があります。相場の賃料に比べ倍以上で借りてくれる場合もあります。
また、建協金を完済する前に、テナントが解約した場合、建協金の残存債務は免除されることが多いです。
ただ、テナントが途中で解約した場合、コンビニ用の建物が残ってしまい、次の入居者を探さなければならないというリスクがあります。
また、次の入居者が決まっても、コンビニ程高い家賃で借りてはくれないでしょう。
多く残っているコンビニ跡地

みなさんも街中で、広い駐車場を持ったコンビニ跡地を見たことがありませんか?
コンビニ大手は良い立地を求めて移転したり、売り上げが伸びない店舗を閉めたりすることがよくあります。
残っているコンビニ跡地はだいたい建協金を借りて作られたものがほとんどです。
建築協力金だけで建物を建てていれば良いですが、必ずしもテナントが全額用意してくれるとは限らず、建築費用の何割かを貸主側で負担している場合もあります。その場合、契約して数年で退去されてしまうと、貸主側の損失にもつながります。
移転のリスクは必ず考慮すること
今回は、土地からコンビニの用途で賃す場合の契約方法2つをご紹介しました。コンビニの用途の場合、他の用途に比べ、賃料が高く設定されやすいですが、その一方で移転・閉店のリスクがあります。
自分の持っている土地より良い立地の物件が近隣に出てきた場合、すぐに移転されてしまう可能性もあります。相当良い立地でない限りはこうしたリスクは充分理解した上で、契約の際には専門家に相談するのがよいでしょう。